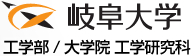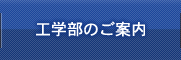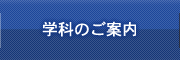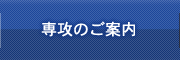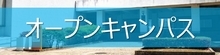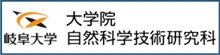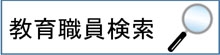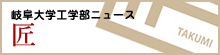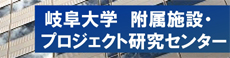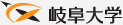【教育】工学部2年生を対象に「技術表現法」を開講 -能動的講義(Active learning) の試み-
2014年5月15日
岐阜大学工学部は2014(平成26)年度より、工学部2年生を対象に「技術表現法」を開講しています.この「技術表現法」の講義形式は、教員から学生へ授業の内容を伝達する受動的な講義形式(Passive learning)ではなく、課題研究、ディスカッション、プレゼンテーションといった、学生の能動的な講義形式(Active learning)を取り入れていることが特長です。
・対象学生:学部2年生全員(4学科 約520名)学科混合8クラス
・担当教員:速水 悟 (電気電子・情報工学科 教授)、亀田 満(非常勤講師)、竹内寛子(同)、宮川 純(同)、川瀬真弓(同)
・開講日:前学期 月曜2限(4クラス)、月曜3限(4クラス)

[本講義のねらい]
「技術表現法」では与えられた課題(テーマ)について、ファシリテーション能力、プレゼンテーション能力およびレポート作成能力をグループワークから学び、
・技術的な内容を論理的に表現する
・課題に対し,明快な論理で構成し、展開する
・聴講者にわかりやすく発表を行い、適切に質疑応答する
といったコミュニケーションに重要な「情報を聞く・読む・書く・伝える力」を高めることをねらいとしています。
また学科ごとにクラス分けをせず、一つのクラスに4学科の学生が混在するクラス編成で講義を受講します。学科混合クラスの実施により学科の枠を超えた人間関係を構築でき、
・人間関係の幅が広がることで学生生活はもとより卒業後の人間関係も充実
・技術者、さらには社会人として基本的な人格形成に役立つ
といったメリットが期待されます。
[講義の様子(二例)]
第4週 グループでアイデアを共有し合意形成(5月8日)
発想からアイデアを生み、あるロジックに沿って制作課題を完成させる活動に取り組みました。従来型のリーダーは配置せず、一人一人がファシリテータとなって、話し合いを動かし、拡散した情報を収束させる方法を学びました。発想からアイデアを生む段階では、ブレーンストーミング(ブレスト)でキーワードをたくさん出します。グループに分かれ、与えられた課題に対し、1枚の付せんに一つずつ各自の意見を書き、大きな紙に貼っていきます。全員の意見がある程度出てきたら、次は収束する段階です。ブレストで得られた多くの意見を合意形成しながら収束させる方法を学びました。
演習では「クイズ制作」を課題としました。まず解答を決めるためブレーンストーミングを実施し、グルーピング、貼り替えを繰り返しながら、解答を一つ選びました。同様に解答を特定するためキーワードを5つ選び、提示する順番を決定し発表しました。キーワードの配列を工夫することで、聴講者をいかにミスリーディングさせるか腕を競い合う場面も見られ、大変活発な回となりました。 第5週 自分・グループの考え・主張を論理的に表現(5月12日)
第5週 自分・グループの考え・主張を論理的に表現(5月12日)
世界標準のプレゼンテーションには、論理的であることが求められます。複雑な問題を正しく理解する読解力、様々な事象を自分の言葉で他の人にわかりやすく表現できる論理的思考力を育成する目的で、ロジカルストラクチャー、パラグラフライティングについて学びました。
・ロジカルストラクチャー(Logical structure):キーワードを書き出し、関連づけて図示化
・パラグラフライティング(Paragraph writing):一つのパラグラフには、複数の根拠、一つの主張および結論を含める
演習では「自炊がよいか、外食がよいか」をテーマにしました。まず話し合いでグループの主張を決め(自炊、外食)、続いて主張の根拠となるキーワード候補を、付せんに書いて沢山列挙し、その中から主となるキーワード(お金がかからない、安い、美味しいなど)を選び出しました。次にロジカルストラクチャーをつくり、発表用原稿をパラグラフライティングで作成し、聴講者に簡潔・明瞭にキーワードを提示しながらプレゼンテーションを行い、活発に主張することができました。
 15週にわたる講義で、課題に関する「情報を読む・聞く」ことで自分の脳にインプットし、その後自分の考えを「書く・伝える」のアウトプット(図示、パラグラフライティング、レポート、ディスカッション、プレゼンテーション)により、自らの考えだけでなく、参加者(学生、教員)の意見を取り入れ、自分の意見を相対的に分析し、ブラッシュアップしてゆきます。
15週にわたる講義で、課題に関する「情報を読む・聞く」ことで自分の脳にインプットし、その後自分の考えを「書く・伝える」のアウトプット(図示、パラグラフライティング、レポート、ディスカッション、プレゼンテーション)により、自らの考えだけでなく、参加者(学生、教員)の意見を取り入れ、自分の意見を相対的に分析し、ブラッシュアップしてゆきます。
関連リンク
■ 岐阜大学Webシラバス 授業科目名に「技術表現法」とご入力下さい。授業内容をご覧いただくことができます。