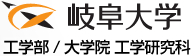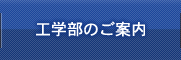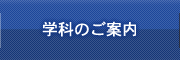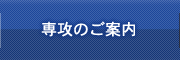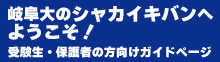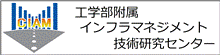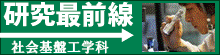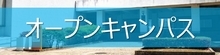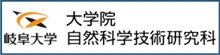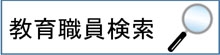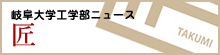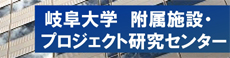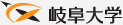髙木朗義教授が「日本自然災害学会 学術賞」を受賞
2025年9月25日
髙木朗義教授(社会システム経営学環・工学部社会基盤工学科)が「日本自然災害学会 令和7年度学術賞」を受賞しました.
研究(総合)題目:XAIを用いた豪雨災害時における住民避難行動に関する要因分析
論文:
XAI(説明可能なAI)を用いた豪雨災害時における住民避難行動に関する要因の交互作用分析、(塚本満朗・髙木朗義の共著)、自然災害科学42巻、特別号、pp.97-119、2023年 https://doi.org/10.24762/jndsj.42.S10_97
画像認識技術Grad-CAMを用いた豪雨災害時における住民避難行動の要因分析、(高田歩武・髙木朗義の共著)、自然災害科学43巻、特別号、pp.207-221、2024年 https://doi.org/10.24762/jndsj.43.S11_207

【日本自然災害学会長 多々納裕一教授(京都大学)と髙木朗義教授】
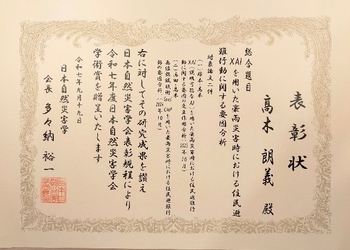
受賞理由:
これまで住民避難行動に対して多様な視点から分析が行われているが、豪雨災害による犠牲者は後を絶たず、住民避難に関する課題は依然として解決しているとは言い難い。特に、これまでの住民避難行動分析では、統計分析に基づき、ある一つの要因が避難行動に影響を与えるのかどうかを明らかにすることが多い。
本研究では、平成30年~令和4年に発生した各豪雨災害時で実施した住民避難行動に関するアンケート調査で収集したデータに対して、機械学習モデルと説明可能なAI(通称XAI)を用いて、住民避難行動に影響を与える要因の組み合わせ(交互作用を考慮した要因)を明らかにした。1件目の論文では、XAIの一種であるPD 分析を適用した。分析の結果として、過去の避難経験や自宅の被災経験、災害時の土砂災害や浸水による自宅の被災などの組み合わせによって避難行動に影響を与えていることを明らかにした。交互作用効果の大きい要因の組み合わせに着目すると、要因単体での影響が0に近い値や負の値を持つような単独では避難行動に影響を与えるとは言えない要因同士が組み合わさることによって、避難行動に影響を与えることが明らかとなった。2件目の論文では、アンケート調査データを画像データに変換し、畳み込みニューラルネットワーク(CNN)を用いて住民避難行動モデルの予測精度を向上させたうえで、画像認識技術におけるXAIの一手法であるGrad-CAM を適用した。
その結果、信頼している人からの避難情報の取得という取得手段、防災に関する情報の深い理解、非常用持出品の準備や家族との話し合いという災害前の準備にあたる要因の組み合わせが災害時に避難行動に影響を与える要因として明らかとなった。この2件の論文で用いているデータは、豪雨災害時における住民避難行動のアンケート調査は、長年に亘って研究グループで検討してきた豪雨災害時に統一的な調査が必要であるということを社会実装して収集したものである。具体的には、平成30年西日本豪雨災害における科研費(突発災害)を切っ掛けに、令和元年~令和4年においても科研費(突発災害)や日本自然災害学会災害調査費補助制度のほか、研究会メンバー個々の研究費などによって得られた複数回の豪雨災害時データを有効活用している。豪雨災害時の住民避難行動に関する要因分析は、これまでも多数の研究が実施されているが、その殆どが統計学的な手法に基づいたものであり、要因間の独立性を前提として、避難行動に影響を及ぼすひとつずつの要因を探るというものである。それに対して本論文は、アンケート調査データに対して避難する/しないを機械学習モデルを用いて推定しており、特に2件目の論文はアンケート調査データを画像データに変換することで機械学習モデルの予測精度を向上させるという着眼点がユニークであり、1件目の論文からの発展も見られる。
推定した機械学習モデルに対して説明可能なAI(通称XAI)を用いることにより、複数の要因の組み合わせが豪雨災害時の住民避難行動に影響を与える要因を分析していることについては、XAI という新規性の高い手法で分析されている点や、既往研究では明らかになっていない新しく意外性を含む結果ではなかったものの、1項目の分析では見い出せなかった避難する/しないとの関連性を指摘した点は学術的な新規性が高く、意義や有益性の大きい研究成果が得られている。
以上の理由により、学術賞の受賞者に相応しいと認められた。
日本自然災害学会 第35回学会賞(令和7年度)